Jeff Buckley 遠い空の歌声

ジェフバックリー、流星の如く現れ、そして散って行った。
ジェフ・バックリーの音楽は、世界的な評価と比べると、ここ日本では少しばかり過小評価されてる向きもある。日本ではこういう事はよくある事で、例えばモータウンレコードの黎明期の立役者であり、特にアメリカの音楽界では、ポップミュージック全体における功労者的な存在のスモーキー・ロビンソンなどはそんな一人かもしれない。
ジェフ・バックリー。才能から言えば、彼の音楽が陽の目を見る27、8歳というのは、他のロックミュージシャンと比較してみると多少長い下積みだったのではないかと思われる。
まさか、ファーストアルバム発表後に自らのアイドル達である、ジミー・ペイジ、ロバート・プラント、ルー・リード、ボブ・ディラン、デイヴィド・ボウイなど錚々たる面々から支持を得ることになるとは、彼はその時分知る由もなかった。
彼の家庭環境に話を移すと、彼の両親は結婚して一年あまりで離婚してしまうが、彼はピアニスト兼チェリストでもある母親に育てられ音楽的には非常に恵まれていたという。そう言えば、最近友人から、ジェフ・バックリーが所蔵していたレコード達がウェブサイトで聴けるようになっているという情報をもらってチェックしてみたが、これがかなり興味深いコレクションなのでここに掲載しておこうと思う。(https://www.jeffbuckleycollection.com)
ところで幼少期に人生で一度しか会う事がなかった父親は、「Once I was」、「Morning glory」、「Song to siren」など後世の様々なアーティスト達からカヴァーされる名曲を産み出した、型破りなフォークシンガー、ティム・バックリー(享年28)であり、また彼も60年代後期、70年代初頭のフォークミュージック界の中で特異的でカリスマ性を持ったアーティストとして名を馳せていた。

残念な事に父親のティムが嗜好したドラッグは快楽と引き換えに、彼自身の命と最愛の息子との大切な時間をあまりにも早く奪い去ってしまう。しかしながら、必ずしもそれはマイナスに作用するのではなく、この空洞なるものこそが芸術の探求に繋がるということなのかもしれない。いずれにせよ、この親子関係に因縁的なもの、または音楽的血統のようなものを感じる人は多いであろう。
その後紆余曲折を経て一躍名を広めることになるのは、奇しくも人生で一度しか会った記憶のない父親のトリビュートコンサートへの参加をきっかけとしてであった。少しづつニューヨークのカフェライブなどでも知る人ぞ知る存在になっていき、コロンビアレコードとの契約を手にすることになる。
そしてとうとう、生前たった一枚のスタジオアルバムであり歴史的名盤である「Grace」を作り上げる。
前述したビッグアーティスト達の後押しも有り、売上げは好調、少しづつ世界に名を轟かせるようになり、グラストンベリー(世界最大規模の音楽フェスティヴァル)等にも出演する。
ジェフはアルバム『Grace』の余韻も冷めやらぬうちに、2枚目のアルバムの製作にとりかかりはじめる。しかし、その真っただ中、順風満帆に見えた青年の魂は無残にも、ツアー中バンドメンバーと立ち寄ったミシシッピ川に奪われてしまう。享年30歳。すべては運命だったのか。神の思し召しだったのか。これまでのことはWikipediaなどを参照いただけば、より詳しく記されていることだろう。

ジェフ・バックリーとの再会
ここで僕自身とジェフ・バックリーとの出会いについて話をしたいと思う。僕は小学生の時に両親にCDプレーヤーを買ってもらったのがきっかけで音楽に心を奪われ、和洋様々な音楽に触れるようになった。しまいにはオタクと言われるくらい、世界中の民族音楽からパンクやクラシックまでありとあらゆるCDやレコードを収集し、バカがつくぐらいCD屋やレコード屋に入り浸り、時には開店から閉店まで全ジャンル全コーナーしらみつぶしに漁りまくっていた時もある。その結果というのもなんだが、二十代からミュージシャンの端くれとして音楽活動もするようになっていった。ジェフ・バックリーの音楽はそれこそ10代の時リアルタイムに触れていて、同時代のNirvana、R.E.M.,なんかと一緒にCDも購入していたし、当時ジェフのこともそれなりの評価をしていた。ここまで彼への思いが高まったのも、何か特別な事があった訳ではないのだが、ある時何かのきっかけで、再び『Grace』を聴こうとプレイヤーを再生した。その瞬間、自分自身の何かが覚醒させられた思いだった。すぐにライナーノートを読み漁り、改めて情報を調べると、自分がこれまで聴いてきたアーティスト達を、彼も聴き愛していた点においても共感出来たし、何よりもジェフの音楽を昔とは全然違う感覚で受け止める事ができた。しばらく彼の音楽から離れている間に、新たな感性が自分自身に備わってきたということでもあるし、あまりにも音楽を手広く知ろうと躍起になっていて振り向いている暇がなかったのかもしれない。とにかく、それがジェフとの音楽的再会であり、それまで研究者のように音楽漁りをしていた僕だったが、彼の音楽にのめり込み一切そんな気が失せてしまった。さらには自分自身の音楽表現の価値なんてあるんだろうか、と思わされるくらいの衝撃を受けた。似たような経験は小学生の時、知ってるつもりという伝記番組で感銘を受けたビリー・ホリデーのCDを購入したものの、まだ自分には全てを理解することができなく、改めて中学生くらいになって素晴らしさを知ったときにも似ていたが、ジェフの場合はそれ以上だった。ほとんど弾けもしないのに、彼への憧れだけで30万くらいのフェンダーのテレキャスターを購入したりもした。とにかく思春期の時に出会った音楽達それ以上に、彼の音は僕に最高のスリルを味合わせてくれた。
何がそんなに刺激的なのか?

それは彼の類い稀なる心象世界の表現の細やかさ、深さ、奥行きの広さである。七色の歌声、天使の歌声と表するものもいるように、その音色の美しさ、ゆらぎを伴い消えてしまいそうな、危うさや儚さを帯びた歌声は圧巻である。アーティストの音楽的傾向を表現する時に、巷に溢れているジャンルレスという言葉は嫌いだが、まさにあらゆる垣根を飛び越えうる感受性と表現力を持ち合わせ、オリジナル、カバー問わず一つの作品をジェフバックリーという個性でまとめあげてしまう力にいつも舌を巻いている。これから初めて彼の作品を聴く人でも、音楽の垣根なく聴いて来た人なら計り知れないスリルとパッションを感じる事ができるはずだが、最初はカバーから入っても良いと思う。とにかくカバーする曲は多岐に渡り、クラシカル、パンク、ワールドミュージック、ポップなどで、映画音楽ではバグダッドカフェの『Calling you』、クラシカルならばPercelの『Dido’s Lament』、パキスタンの伝説的歌い手Nusrat Fateh Ali Khanの『Yeh jo halka saroor hae』、FolkではBob Dylan『Just like woman』などなど枚挙に暇が無いが、彼を語るには忘れてはいけないカバー曲がLeonard Cohenの『Halleluja』である。この曲で彼を知ってる人は多いはず。本来カバー曲というのはあくまでカバー曲である事が多いのだが、彼の解釈はオリジナルを凌駕するというか、新たな息吹を作品に与える事ができるのだ。

ジェフ・バックリーはジミ・ヘンドリクス、ビリー・ホリデー、マイルス・デイビス、ボブ・ディランなどに代表されるような西欧音楽のレジェンドたちと肩を並べる存在であり、更に言えば、世界のポップス界においても、音楽の歴史を遡っても、間違いなく輝かしい功績を残した一人であると言える。1990年代という既に大量消費社会となって久しい中で、玉石混淆とした大量消費的なショービジネスのど真ん中に、たったひとつの明らかなる音の宝石を残してくれた数少ない貴重な表現者であり、世の中の趨勢にも左右されない、ひとつの新たな音楽の可能性を示したパイオニアでもあると思う。
音楽を愛するものならば一度は彼の音楽を聴いて欲しい。歌にギターにメロディに、パッションという血流が静かに、でも確かに行きわたっている。
思いが故に言葉を尽くしてはみたが、言葉は時に本質から遠ざけてしまうものだ。
何が言いたいか、それは彼の細胞という細胞の囁きに、叫びに、泣き声に耳を傾けて欲しい。
遠き空の天使の歌声よ永遠に。
written by セキグチタケオ
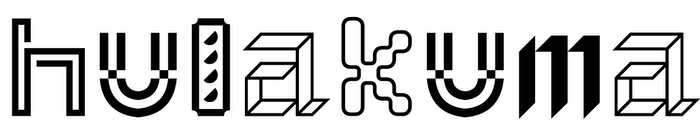




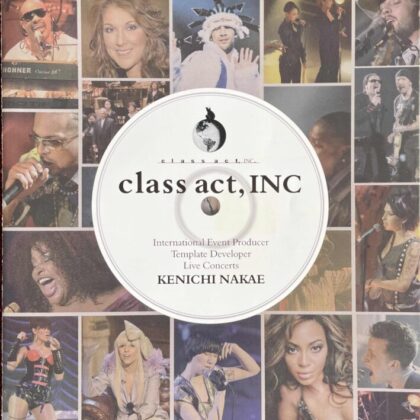


コメントを残す